
『もしも脳梗塞になったなら』
実体験を元に闘病生活伝える
発症から手術・リハビリ・回復まで
闘うことより受け止めることの重要性 |
|
一般に健康に関する映画作品は、ジャンルとして難病ものの範ちゅうに入れられる。今回紹介する『もしも脳梗塞になったなら』(2025年/102分)は、脳梗塞とはどのような症状なのか、実際に発症した映画監督の経験を題材に自らが映画化した作品である。同病について漠然と見聞きすることはあるが、その詳細については、正確なことは知らない人が多いのではないだろうか。
現役で活躍中の映画監督・太田隆文の経験をドキュメンタリー・タッチで描く本作は、脳梗塞の実態、患者としての苦しみ、そして周囲の反応ぶりに触れ、死に至る大変な病気であることを実感させられる。この太田監督の闘病生活の有様を、窪塚駿介が主役の大滝隆太郎として演じる。
太田監督は2023年に脳梗塞を発症後、2年で3度の手術を受ける。先ごろ開かれた試写会で、同監督は舞台であいさつに立ち、作品製作の経緯を話す。映画化の動機は「自身の闘病生活が誰かの役に立てば」との思いからである。彼は休みも取らず映画監督業を続けた過重労働の大変さについて触れる。
1人暮らしの彼、突然、脳梗塞を発症、この時点で彼の闘病生活が始まる。働き過ぎが原因で、まず両目とも半分失明する。画面上はスクリーンの右がぼやけ、画面が薄くなる方法で、半失明状態を見る者に伝える。なかなか凝った趣向だ。
おまけに、言葉がうまく出ない。心臓の機能が20%まで低下、もう、この段階で死に体と思われるほど、多種の病気が彼に襲い掛かる。
検査はもちろんのこと、治療、入院、手術、リハビリの日々を2年間送る。筆者が不思議に思うのは、手術の段階まで通院治療で、入院していないことである。1人暮らしで、苦心惨憺(さんたん)の末の食糧買い出しをするような生活は、並の苦痛ではない。
 |
主人公、大滝隆太郎(左)病室で
(C)シングルアンドウィル 青空映画舎 ※以下同様
|
 |
試写会での主人公の妹さくら
|
 |
主人公の友人雀(すずめ)
|
 |
母・明子と主人公の幼少時
|
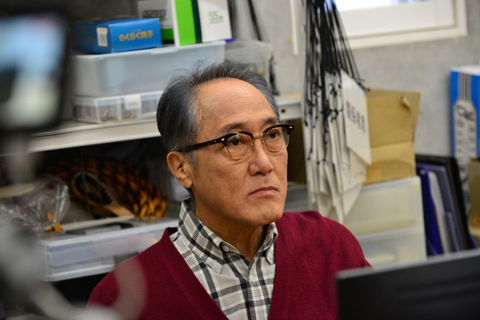 |
霧山(主人公の同病の友人)
|
脳卒中、脳梗塞、脳出血、多くの方々にとりそれぞれの区別は可能であろうか。まず、脳卒中とは、脳に血流が流れなくなることによる、脳の神経細胞が壊死(えし)する病気全般を示す語である。その原因によって、脳梗塞、脳出血などに分類される。
脳の神経細胞の障害により、病状として半身のしびれや麻痺(まひ)、言語障害といった病状が現れる。原因として5大リスクが挙げられる。それらは高血圧、糖尿病、脂質異常症、不整脈、喫煙がある。
太田監督は1961年和歌山県生まれ。大学は米国ロサンゼルスの南カリフォルニア大学(USC)映画科出身。帰国後の2003年、大林宜彦監督に師事、いわゆる大林組の一員となる。
監督第1作は、故郷・和歌山を舞台にする『ストロベリーフィールズ』(2006年)で、その後、地方を舞台にする青春映画の製作、監督・脚本も務める。いわば、地味な中堅監督である。そして、2023年に脳梗塞を発症、再起不能と思われたが、回復後、本作を発表、現在に至る。
本作で役の上の大滝隆太郎は、映画監督として活躍し、とにかく、「目指せハリウッド」を目標に掲げ、気合が入っている。病因は、17年間休みなしの働き過ぎである。
貧乏な弱小プロダクションの映画作り、毎回、監督だけでなく、脚本、プロデューサーなども務め、気が付けば脳梗塞の発症となる。この元気者の彼、友人たちは押しなべて、同様な反応を示す。「あいつが倒れるはずがない」とばかりに。
太田監督は本作の製作に当たり、脚本は何とかこなすが、当時は文字を読むことは体力的に無理であった。撮影時は未だ心臓機能が危険値であるが、クランクインは担当医に内緒である。体力がない彼にとり長時間撮影は難しく、撮影時の体力消耗は、はなはだしいものだ。
太田監督自身は、本物の病人の経験者であり、自分だからこのリアルな病人生活が描けることを確信する。
張り切り屋の重病、しかも命にかかわる危険を、やっとの思いですり抜ける大滝隆太郎に対し、周囲の反応は表面的なのだ。この友人たちの思いやりのない情けの薄さこそ、太田監督が描きたかったところの1つである。
大滝の場合、まず、ひどい咳に悩まされる。横になると咳、そのうち目の前が良く見えなくなる。風邪らしい症状を怪しみ通院。ここで視力の不調を訴えるが、最初医師は風邪と診断し、型通りの処理となる。次いで、目の不調を他の医師が診察すると、大変重い症状でおそらく半分の失明は治らぬとの見立て。医師の診断に大滝はがっくり、そして在宅のままの状態は続く。
ドキュメンタリー・タッチで話が運ばれ、見る側に徐々に脳梗塞の重大さを理解させる。病気の進行をリズムの核とする太田監督のハナシの運びは上首尾で、どんどん体内に脳梗塞が浸透する感じ。
作中、大滝へは見舞いの電話やメールがポツポツと入りだす。見舞いの言葉は本当に難しく、時に的外れなアドバイスもあり、大滝をイライラさせる。身もふたもない言い方だが、見舞いの言葉、1,2度なら「退院おめでとう」で済むが、大滝監督の場合、長期にわたり、見舞う方も何を言えばいいのか分からなくなる。
例えば、1人の友人が、足元がおぼつかない大滝を買い物のため自分の車で送迎するが、何度目からは「仕事が変わった」と言い難そうに告げる。送迎する方も相当な負担であり、助ける方が離れ、彼も落胆する場面である。
送迎の件以外に、電話での対応も難しい。彼は、一方的に病状の説明をし、自分の窮状を訴えるが、相手方も、同じ話を何度も聞かされウンザリの態。彼もイライラがつのるが、この辺り、多くの闘病経験者は身に覚えがあることだろう。見舞う方も、行って励ましたい気持ちはあるが、彼は「お大事に」の言葉自体空虚なものと感じる。
見舞いについて「お大事に」が通用しないことはお互い分かっている。柄の悪い言い方だが「退院したら一緒に温泉へでも行こうか」くらいだと、患者の目の色も変わり有効だとの説もある。黙って距離を置くより手はないと思わざるを得ない。
残酷な結果も出る可能性はあるが、この仕方しかないことは、太田監督もはっきりと感じ取っているのではなかろうか。買い物もままならず、押し入れに放りっぱなしの缶詰の乾パンを1人でムシャムシャ食べる場面の虚しさが象徴している。
つらい病気を1人で受け止め、病気と闘うことよりは、起こることにただただついて歩くこと、それが、太田監督が得た結論であろう。病気と果敢に闘い、悪くすれば命を落とす危険をおかしながらの奮闘ぶりも結構だが、皆の後について行く、受け止める闘病もありとする心情がくみ取れる。
実生活で、親しい友人が病に伏す場合を想像してみれば、もう、そこには選択の問題しかないというのが、作り手の本心かも知れない。この問題は難しい。
太田監督自身、病気と接するというより、むしろ、受け止めることしかない闘病生活であり、そこからの生還である。病気と闘うには体力的に不可能で、1つひとつの症状について行くことで手いっぱいと言えよう。
しかし、彼は諦めず、病と付き合うことで命を長らえたのである、これも、1つの生きる方法である。そのあたりを伝えたく映画化に踏み切ったのであろう。
見る側は、脳梗塞について学び、併せて付き合い方を知ることになる。受け止め方を学ぶ上で、ドキュメンタリー・タッチは有効であることが、作品から受け取れる。
(文中敬称略)
《了》
12月20日より新宿ケイズシネマほかにて全国順次公開
映像新聞2025年12月1日掲載号より転載
中川洋吉・映画評論家
|
